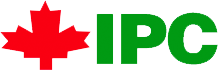エネルギーフィードバックユニットのサプライヤーは、周波数変換器はデバッグや使用中に様々な問題に遭遇することが多く、その中で最もよくあるのが過電圧であることをお客様に注意喚起しています。過電圧が発生すると、内部回路の損傷を防ぐため、周波数変換器の過電圧保護機能が作動し、周波数変換器の動作が停止し、機器が正常に動作しなくなります。
したがって、過電圧を除去し、故障の発生を防止するための対策を講じる必要があります。周波数変換器とモーターの適用シナリオが異なるため、過電圧の発生原因も異なるため、具体的な状況に応じて適切な対策を講じる必要があります。
周波数変換器および回生ブレーキにおける過電圧の発生
周波数変換器のいわゆる過電圧とは、さまざまな理由により周波数変換器の電圧が定格電圧を超える状況を指し、主に周波数変換器の DC バスの DC 電圧に現れます。
通常動作時、周波数変換器の直流電圧は三相全波整流後の平均値です。380Vの線間電圧を基準に計算すると、平均直流電圧Ud=1.35U line=513Vとなります。
過電圧が発生すると、DCバス上の蓄電コンデンサが充電されます。電圧が約700V(モデルによって異なります)まで上昇すると、周波数変換器の過電圧保護が作動します。
周波数変換器における過電圧の主な原因は、電力過電圧と回生過電圧の 2 つです。
電源過電圧とは、過剰な電源電圧によって直流バス電圧が定格値を超える状況を指します。現在、ほとんどの周波数変換器の入力電圧は最大460Vに達するため、電源に起因する過電圧は極めて稀です。
この記事で議論される主な問題は、過電圧の再生です。
回生過電圧が発生する主な原因は、GD2(フライホイールトルク)の負荷が減速するときに、周波数変換器によって設定された減速時間が短すぎることです。
モータは下降時に外力(ファンやストレッチングマシンなど)や潜在的な負荷(エレベーターやクレーンなど)の影響を受けます。これらの理由により、モータの実際の速度は周波数変換器の指令速度よりも高く、モータの回転子速度が同期速度を超えることを意味します。このとき、モータの滑り率は負であり、回転子巻線が回転磁界を切断する方向はモータの状態と逆になります。それによって発生する電磁トルクは、回転方向を妨げる制動トルクです。そのため、電動モータは実際には発電状態にあり、負荷の運動エネルギーが電気エネルギーに「回生」されます。
回生エネルギーはインバータのフリーホイールダイオードを介してインバータの直流エネルギー貯蔵コンデンサに充電され、直流バス電圧の上昇を引き起こします。これを回生過電圧と呼びます。回生過電圧の過程で発生するトルクは、元のトルク、つまり制動トルクとは逆のトルクです。したがって、回生過電圧の過程は回生ブレーキの過程でもあります。
つまり、回生エネルギーをなくすことでブレーキトルクが増加します。回生エネルギーが大きくない場合、インバータとモーター自体には20の回生ブレーキ容量があり、この部分の電気エネルギーはインバータとモーターによって消費されます。このエネルギーが周波数変換器とモーターの消費容量を超えると、直流回路のコンデンサが過充電され、周波数変換器の過電圧保護機能が作動して運転が停止します。このような状況を回避するには、回生ブレーキの目的であるブレーキトルクを増加させながら、このエネルギーを適時に処分する必要があります。
周波数変換器の過電圧防止対策
過電圧の発生原因が異なるため、対策も異なります。駐車中に発生する過電圧現象については、駐車時間や場所に特別な要件がない場合は、周波数変換器の減速時間を延長するか、フリーパーキングで解決できます。フリーパーキングとは、周波数変換器が主開閉器を遮断し、モーターが自由に滑走して停止することを指します。
駐車時間や駐車場所に一定の要件がある場合は、DC ブレーキ機能を使用できます。
DC ブレーキ機能は、モーターを特定の周波数まで減速し、モーターの固定子巻線に DC 電力を印加して静磁場を形成します。
モーターローター巻線はこの磁界を遮断し、制動トルクを発生させます。この制動トルクは負荷の運動エネルギーを電気エネルギーに変換し、モーターローター回路内で熱として消費します。そのため、このタイプの制動はエネルギー消費型制動とも呼ばれます。DCブレーキのプロセスは、実際には回生ブレーキとエネルギー消費ブレーキの2つのプロセスで構成されています。この制動方法の効率は回生ブレーキの30~60%に過ぎず、制動トルクも比較的小さくなります。モーターへのエネルギー消費は過熱を引き起こす可能性があるため、制動時間は長すぎないようにする必要があります。
さらに、直流ブレーキの始動周波数、制動時間、制動電圧はすべて手動で設定され、回生電圧のレベルに基づいて自動的に調整することはできません。そのため、直流ブレーキは通常運転中に発生する過電圧には使用できず、駐車時の制動にのみ使用できます。
減速時(高速から低速まで無停止)に負荷のGD2(フライホイールトルク)が過大になることで発生する過電圧に対しては、減速時間を適切に延長する方法を採用することで解決できます。実は、この方法も回生ブレーキの原理を利用しています。減速時間を延長することで、負荷の回生電圧によってインバータの充電速度を制御するだけで、インバータ自体の回生ブレーキ能力を適切に活用できます。外力(位置エネルギーの放出を含む)によってモータが回生状態になる負荷については、正常にブレーキ状態のまま動作するため、回生エネルギーが大きすぎて周波数変換器自体で消費できません。そのため、直流ブレーキを使用したり、減速時間を延長したりすることはできません。
回生ブレーキは直流ブレーキに比べて制動トルクが高く、その大きさは周波数変換器の制動ユニットによって負荷の必要制動トルク(すなわち回生エネルギー量)に応じて自動的に制御されます。そのため、回生ブレーキは通常運転時に負荷に制動トルクを供給するのに最適です。
周波数変換回生ブレーキ方式:
1. エネルギー消費タイプ:
この方式は、周波数変換器の直流回路に制動抵抗器を並列に接続し、直流バス電圧を検出してパワートランジスタのオン/オフを制御するものです。直流バス電圧が約700Vに上昇すると、パワートランジスタが導通し、回生エネルギーを抵抗器に送り込み、熱エネルギーとして消費することで、直流電圧の上昇を抑制します。回生エネルギーを利用できないため、エネルギー消費型に分類されます。エネルギー消費型であるため、直流ブレーキとの違いは、モーター外部の制動抵抗器でエネルギーを消費するため、モーターが過熱せず、より頻繁に動作できることです。
2. 並列DCバス吸収型:
各モーターに周波数変換器が必要で、複数の周波数変換器が系統側変換器を共有し、すべてのインバータが共通のDCバスに並列接続されるマルチモーター駆動システム(ストレッチングマシンなど)に適しています。このシステムでは、1つまたは複数のモーターがブレーキ状態で正常に動作していることがよくあります。ブレーキ状態のモーターは他のモーターに引きずられて回生エネルギーを発生させ、その回生エネルギーは並列DCバスを介して電動状態のモーターに吸収されます。完全に吸収できない場合は、共有ブレーキ抵抗器を介して消費されます。ここで発生した回生エネルギーは部分的に吸収・利用されますが、電力系統にはフィードバックされません。
3. エネルギーフィードバック型:
エネルギーフィードバック型インバータ系統側コンバータは可逆性を有しています。回生エネルギーが発生した場合、可逆コンバータは回生エネルギーを系統にフィードバックすることで、回生エネルギーを最大限に活用することができます。しかし、この方式は高い電源安定性を必要とし、突然の停電が発生すると、反転・転流が発生します。