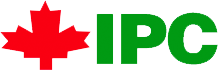周波数変換器ブレーキユニットのサプライヤーは、周波数変換器技術の強力な推進と周波数変換器販売業者の積極的なプロモーションにより、一部の産業企業が周波数変換器の使用を無意識のうちに省エネ・節電と同一視していることを指摘しています。しかし、実際の使用においては、様々な状況に直面し、多くの企業が周波数変換器が適用されるすべての場所で省エネ・節電が実現できるわけではないことに徐々に気づき始めています。では、このような状況の原因は何でしょうか?また、人々が周波数変換器について抱いている誤解は何でしょうか?
1. 周波数変換器は、あらゆるタイプのモーターに使用すると電力を節約できます。
周波数変換器が省エネ効果を発揮できるかどうかは、負荷の速度制御特性によって決まります。遠心機、ファン、水ポンプなどの二次トルク負荷の場合、モータ出力P∝TnおよびP∝n3を満たす必要があります。つまり、モータ軸の出力は速度の3乗に比例します。二次トルク負荷の場合、周波数変換器の省エネ効果が最も顕著であることがわかります。
ルーツブロワーなどの定トルク負荷の場合、トルクは回転速度に依存しません。一般的には、排気口を設け、バルブで制御します。風量が需要量を超えると、超過風量を排出することで調整を行います。この場合、速度制御運転が可能で、省エネ効果も得られます。また、定電力負荷の場合、電力は回転速度に依存しません。このような場合、周波数変換器を使用する必要はありません。
2. エネルギー消費量の計算方法の誤りに関する誤解
多くの企業は、省エネ効果を計算する際に、皮相電力に基づく無効電力補償をよく用います。例えば、モータが商用周波数条件下で全負荷運転しているとき、測定された動作電流は194Aです。可変周波数速度制御を使用すると、全負荷運転時の力率は約0.99に上昇します。このとき、測定された電流は173Aです。電流が減少する理由は、周波数変換器の内部フィルタコンデンサがシステムの力率を改善するためです。
皮相電力計算による省エネ効果は以下のようになります。
ΔS=UI=380×(194-173)=7.98kVA
省エネ効果はモーター定格電力の約11%です。
実際、皮相電力Sは電圧と電流の積です。同一電圧条件下では、皮相電力の変化は電流の変化に比例します。回路内のシステムリアクタンスを考慮すると、皮相電力はモータの実際の消費電力を表すのではなく、理想的な条件下での最大出力容量を表します。モータの実際の消費電力は通常、有効電力として表されます。
モーターの実際の消費電力は、モーターとその負荷によって決まります。力率を上げてもモーターの負荷は変化せず、モーターの効率も変化しません。したがって、モーターの実際の消費電力は変化しません。力率を上げた後、モーターの動作状態、固定子電流、有効電流と無効電流に変化はありませんでした。では、力率はどのように改善されるのでしょうか?その理由は、周波数変換器内のフィルタリングコンデンサにあり、モーターの消費電力の一部は、フィルタリングコンデンサによって発生する無効電力です。力率の改善は、周波数変換器の実際の入力電流を削減し、電力網の線路損失と変圧器損失も削減します。上記の計算では、実際の電流を使用して計算していますが、有効電力ではなく皮相電力を計算しています。したがって、皮相電力を使用して省エネ効果を計算するのは誤りです。
電子回路である周波数変換器自体も電力を消費する。
周波数変換器の構成からわかるように、周波数変換器自体にも電子回路が搭載されているため、動作中に電力を消費します。高出力モーターと比較すると消費電力は少ないものの、それ自体の消費電力は客観的な事実です。専門家の計算によると、周波数変換器の最大自己消費電力は定格電力の約3~5%です。1.5馬力のエアコンは20~30ワットの電力を消費し、これは点灯中の照明に相当します。
まとめると、周波数変換器は商用周波数で動作する際に省エネ機能を発揮することは事実ですが、その前提条件として、第一に、高出力でファン/ポンプ負荷であること、第二に、装置自体が省エネ機能(ソフトウェアによるサポート)を備えていること、第三に、長期連続運転が可能であることが挙げられます。これら3つの条件が、周波数変換器が省エネ効果を発揮できる条件です。
省エネと消費削減は製造業の永遠の目標であり原則ですが、工業企業にとっては、どのような状況で周波数変換器を使用するべきか、どのような場合に周波数変換器の使用が適さないかを理解し、周波数変換器の全体構成を総合的に検討する必要があります。周波数変換器の過剰な構成による高調波被害は周知の事実です。したがって、省エネ、消費削減、持続可能な発展という戦略を真に実現するためには、周波数変換器を合理的に使用することが重要です。